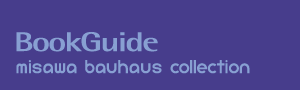ヨゼフ・アルバース(英語表記ではジョセフ・アルバース)は、バウハウスに学生として入学したのちバウハウスで教鞭をとり、造形基礎教育に多大な貢献をした人です。バウハウス閉鎖後渡米し、ブラックマウンテンカレッジ、次いでエール大学等で教壇に立ち、色とかたちの追求を続けました。画家としてもその後のオプ・アートに大きな影響を与える作品を生みだしています。彼の生涯を貫いていたのは教育者としての志でした。ご紹介するのは、色とかたちに興味のあるすべての人に、ぜひ手に取っていただきたい本です。
3-1『色彩構成 −配色による創造-』
ジョセフ・アルバース著/白石和也訳
ダヴィッド社:1978年
1,500円 ISBN:4-8048-0047-6 C0072
3つの壺の中の(1)熱い湯 (2)ぬるい湯 (3)冷たい水 を用意して、中に手を入れる順番を変えてみると、(1)→(2)の順に手を入れた人は(2)が冷たいと感じ、(3)→(2)の順なら(2)を温かいと感じるだろう。
アルバースはこんな例をだして、色彩もこれと同じように、互いの相互関係によって、感じ方が変わるのだと説明しています。彼は生涯、色の研究をおこないましたが、そのテーマはこの本の原題のとおり、「色彩の相互作用(Interaction of Color)」でした。隣との関係によって、色は前進・後退し、ある時は透けて見える。頭で理解する色彩論ではなく、具体的で身近な例を積み重ねることで色彩の豊かな働きがわかるようになっています。この本を読むと、彼の代表作である"Homage to the Square(方形への敬意)"の作品群が、この色彩学の豊かな成果であると同時に素晴らしい教材であるということにも気付くのです。
3-2『ジョセフ・アルバースの視覚世界 −直線のみで−』
ジョセフ・アルバース、フランソワ・ブシェ著/首藤順蔵訳
玉川大学出版部:1988年
3,296円 ISBN:4-472-07901-1 C3072
まずはこの本を手にとってページを繰り、作品図版をみてみましょう。直線を組み合わせたさまざまな図形は、単純に見えて深い異次元をはらんでいます。視覚の混乱。視点を動かすとその図形の奥行きはとたんに逆転し、見せかけの空間は運動を繰り返す。遠近法は、二次元に視覚的な空間をもたらしましたが、アルバースの作品は、錯視のメカニズムを利用して、複数の線の交差がもたらす空間の虚構をあらわにしているのです。彼は、錯視の効果が他の影響を受けないよう、定規と烏口で ニュアンスを持たない線をひくという厳しい制約を自らに課しました。従って、このシリーズの作品は、素っ気ない線の組合せからできています。しかし、そのただの線は、ずっと見ていても飽きない豊かな空間とリズムを持っているのです。
アルバースの言葉を豊富に掲載し、美術家フランソワ・ブシェによる解説を手がかりに、彼が追求した形態の意味を解いていく本です。